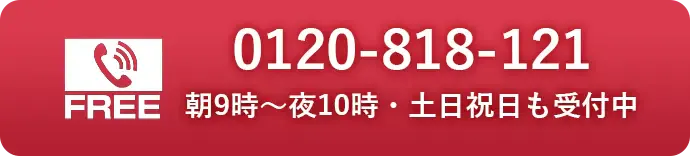- 成年後見の申立てから審判が下されるまで、どのくらいの期間がかかりますか?
-
一般的には、およそ2ヵ月~4ヵ月が目安とされています。
ただし、親族間で対立があったり、財産の額や種類が多かったりする場合は、話合いや調査などに時間がかかり、半年以上に及ぶこともあります。なお、手続の基本的な流れは以下のとおりです。
①判断能力に関する診断書の発行
②本人情報シート(※)の発行
③後見人の候補者の選定と申立て
④申立人や候補者などの面接
⑤医師による鑑定
⑥成年後見人の選任・完了※福祉関係者(ケアマネージャーなど)が、ご本人の生活状況や心身の状態に関して、具体的な状況を記載した書類
- 後見人への報酬は誰が支払いますか?
-
基本的には、被後見人の財産のなかから支払われます。
申立てを行ったご家族や、ほかのご親族が直接支払う必要はありません。報酬が支払われるまでの手順は、以下のとおりです。
①後見人による報酬付与の申立て
②裁判所による金額の決定
③ご本人の財産から支払い①後見人による報酬付与の申立て
後見人は、裁判所に対して「報酬付与の申立て」を行います。
1年間の仕事内容を裁判所に報告するタイミングで、併せて申し立てることが多いです。②裁判所による金額の決定
裁判所は、後見人が行った仕事内容(財産管理の複雑さ、身上保護の状況など)や、ご本人の財産額などを総合的に考慮して、報酬額を決定します。
③被後見人の財産から支払い
決定された報酬額を、被後見人の財産から受け取ります。
判断能力が低下している被後見人では手続が難しいため、後見人自身が預金口座などから引き出します。
- 後見人には、家族が選任されますか?
-
後見人には、必ずしもご家族が選ばれるとは限りません。
裁判所はさまざまな事情を考慮して、後見人にふさわしい人を選任するからです。なお、後見人にご家族が選ばれるケースは、そう多くないのが実情です。
最高裁事務総局家庭局による2024年の統計(※)によると、成年後見人等に親族が選任されたケースは全体の約17%で、残りの約83%は弁護士などの専門家が選任されています。
※参考:成年後見関係事件の概況―令和6年1月~12月―というのも、そもそも専門家の選任を希望するケースや、裁判所が専門家の関与が必要だと判断するケースが多いからです。
後見人に専門家を選ぶべきケースとしては、以下のような状況が該当します。
- 財産が多く、管理が複雑な場合
- 親族間に対立があり、トラブルに発展する可能性がある場合
- 不動産の売却など、専門的な手続が予定されている場合
- 家族信託の契約は誰と結んでもいいですか?
-
法律上は、以下に当てはまる人以外であれば、基本的に誰とでも結ぶことができます。
- 未成年者
- 成年被後見人、被保佐人(判断能力が不十分とされている人)
だからといって、「契約相手は誰でもいい」というわけではありません。
特に重要なのは、「受託者」を誰にするかという点です。
受託者は、大切な財産の管理・処分をする権限を持つことになります。そのため、責任感が強く信頼ができる方、そしてある程度の事務処理能力のある方を選ぶべきです。
- 成年後見人には誰がなれますか?
-
成年後見人には、ご家族やご親族でもなれますし、弁護士などの専門家が選ばれることもあります。
ただし、以下の点には注意すべきです。①ご家族・ご親族がなる場合
親族を後見人の候補者として申し立てることができますが、必ずしも選任されるとは限りません。
②法律・福祉の専門家(第三者後見人)がなる場合
財産額が大きかったり、親族間で対立があったりするなど、複雑な事情がある場合は、弁護士など専門家が選ばれることがあります。
中立的な立場から、専門的な知識によって後見業務を行うためです。一方、以下に当てはまる方などは、成年後見人になれないと法律によって定められています。
- 未成年者
- 過去に家庭裁判所から後見人などを解任されたことがある人
- 破産者
- 被後見人に対して訴訟をしたことがある人、またその配偶者や子など
- 遺言書を作成していても、家族信託はできますか?
-
遺言書を作成していても、別途、家族信託の契約を結ぶことは可能です。
それぞれ役割が異なるため、併用することで、よりきめ細やかな財産管理や承継を実現できる場合もあります。注意すべきは、「遺言の効力が信託財産に影響しない」という点です。
家族信託に含めた財産の名義は、形式的に委託者(親など)から受託者(子どもなど)へ移ります。
つまり、信託した財産は相続財産から切り離されるのです。たとえば、「A銀行の預金を長男に相続させる」という遺言書を残したとしましょう。
しかし、そのA銀行の預金が信託財産になっていた場合、信託契約のほうが優先され、遺言書のその部分の効力は失われることになります。
- 家族信託に含められる財産の種類に制限はありますか?
-
法律上、信託できない財産がいくつかあります。
預金
銀行に預けているお金をそのまま信託することはできません。
委託者が一度預金を下ろして、信託口座に入金することで初めて信託対象となります。農地
農地法による厳しい規制があり、いくつかの条件を満たさない限り、原則として信託はできません。
年金受給権や生活保護受給権
年金を受給する権利などは、本人にのみ帰属する権利のため、他人に譲渡したり信託したりすることができません。
マイナスの財産
原則として、借金などの債務を信託することはできません。
- どのような場合に家族信託が役立ちますか?
-
家族信託は、特に以下のようなケースで役立ちます。
- 認知症などによる「資産凍結」への対策
- 数世代にわたる資産承継
- 障がいを持つ子の「親なき後」の生活支援
- 円滑な事業承継によるリスク防止
認知症などによる「資産凍結」への対策
委託者(親など)の代わりに、受託者(子どもなど)が財産を柔軟に管理・活用できる点が大きなメリットです。
委託者がたとえ認知症になっても、口座が凍結されたり、不動産を売却できなくなったりする事態を防げます。数世代にわたる資産承継
家族信託なら、「自分の遺産は長男に、長男の次は孫に」というように、数世代先の資産承継まで指定できます。
一方、遺言ではご自身の次の相続先までしか指定できません。障がいを持つ子の「親なき後」の生活支援
障がいを持つお子さんの場合、いくら資産を残しても管理ができなかったり、騙されたりするおそれがあります。
信頼できる親族と家族信託の契約を結ぶことで、お子さんの生活を守ることができます。円滑な事業承継によるリスク防止
後継者を受託者として、自社株式を信託しておくことで、経営者に万が一のことがあっても、経営に悪影響が出るリスクを防ぎやすくなります。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121