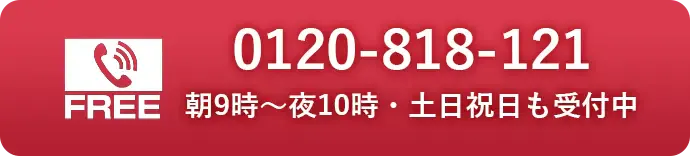- 相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?
-
以下のように対応する必要があります。
①未分割のまま、期限内に申告・納税する
②遺産分割協議を成立させる
③「更正の請求」を行い、税金の還付を受ける①未分割のまま、期限内に申告・納税する
遺産分割協議がまとまらなくても、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10か月)は延長されません。
したがって、「法定相続分」で財産を取得したと仮定して相続税額を計算し、申告・納税まで行いましょう。
なお、申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」という書類を必ず添付してください。②遺産分割協議を成立させる
申告後、あらためて相続人同士で話合いを行い、遺産分割協議を成立させます。
先ほどの分割見込書の提出によって、申告期限から3年間の猶予が与えられます。③「更正の請求」を行い、税金の還付を受ける
遺産分割が正式に決まったあと、その内容に基づいて税額を再計算し、税務署に対して「更正の請求」という手続を行います。
この手続の際に、本来適用できるはずだった税額控除の特例なども改めて申請します。
手続が認められれば、最初に納めた税金との差額が還付され、払い過ぎた税金が戻ってくることになります。
- どのような財産が相続税の対象になりますか?
-
対象となる財産は、以下のとおりです。
- 金融資産や不動産など
- みなし相続財産
- 一定期間内の生前贈与財産
金融資産や不動産など
金融資産:現金、預貯金、株式、投資信託などの有価証券
不動産:土地、建物(自宅、マンション、アパートなど)
動産:自動車、貴金属、骨董品、家財道具など
その他:ゴルフ会員権、著作権、貸付金などみなし相続財産
「みなし相続財産」とは、法律上、相続財産ではないものの、実質的に相続財産と同じとみなされ、課税対象となる財産です。- 生命保険金(死亡保険金)
- 死亡退職金
※これらには「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。
一定期間内の生前贈与財産
亡くなる前に贈与された財産も、以下のように相続税の対象となる場合があります。【2023年12月31日までに行われた贈与】
被相続人が亡くなってから3年以内の金額はすべて相続税がかかる【2024年1月1日以降に行われた贈与】
①被相続人が亡くなってから3年以内の金額はすべて相続税がかかる
②被相続人が亡くなってから4年前~7年以内の金額は、その期間の贈与合計額から100万円を控除した金額に相続税がかかる
- 相続税の控除や特例にはどんなものがありますか?
-
代表的なものは以下のとおりです。
- 基礎控除
- 相続税の配偶者控除
- 小規模宅地等の特例
- 生命保険金・死亡退職金の非課税枠
基礎控除
もっとも基本的な非課税枠です。遺産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
控除額は、「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で計算します。相続税の配偶者控除
配偶者が相続した財産のうち、1億6,000万円または配偶者の法定相続分のいずれか多い金額まで、相続税がかからないという制度です。
小規模宅地等の特例
亡くなった方が住んでいた土地や、事業をしていた土地などを相続した場合に、その土地の評価額を最大で80%減額できる制度です。
生命保険金・死亡退職金の非課税枠
通常、生命保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、それぞれに非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)が設けられています。
なお、控除制度や特例の多くは、期限内(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月)に申告を行うことが条件となっていますので、ご注意ください。
- 銀行の預金は相続税がかかりますか?
-
亡くなった方(被相続人)名義の銀行預金にも、相続税はかかります。
ただし、預金も含め、取得した遺産の合計額が、基礎控除額以下であればかかりません。
基礎控除額は「3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)」で求められます。なお、相続税を計算する際、預貯金の種類によって以下のように評価方法は異なります。
普通預金
亡くなった日(相続開始日)の最終残高を評価額として計算。
定期預金
亡くなった日の最終残高に、その日時点で解約した場合に受け取れる利息(税引後)を加えた金額を評価額として計算。
名義預金
亡くなった方が、生前に配偶者やお子さん、お孫さんの名義で口座を作り、そこにご自身の資金を移している場合は注意が必要です。
たとえ名義が異なっていても、実質的に亡くなった方の財産と判断されて、相続税の対象となる可能性があります。
- 相続発生後にできる相続税対策はありますか?
-
以下のような対策が考えられます。
- 特例制度などを活用する
- 二次相続まで見据えて遺産分割する
- 土地の評価額を正しく下げる
特例制度などを活用する
たとえば、以下の特例制度はある程度の節税効果を期待できます。
小規模宅地等の特例:条件を満たす土地の評価額を、最大80%減額できる
相続税の配偶者控除:所定の金額以下なら、配偶者に相続税が課されない二次相続まで見据えて遺産分割する
二次相続とは、相続が相次いで発生している場合に、2番目に発生した相続のことです。
二次相続では、配偶者控除が適用できなかったり、法定相続人が1人減ったりすることで、相続税の負担が大幅に増えることがあります。
そのため、最初の相続だけでなく、二次相続の税額まで考えて遺産分割すると、トータルの税負担を抑えられることがあるのです。土地の評価額を正しく下げる
土地の評価は専門性が高く、評価方法によって金額が変わります。
そのため、土地の形状を考慮するなど、適切な方法で評価を行うと評価額が下がることがあるのです。ただし、土地の評価には専門的な知識を要するため、相続に詳しい税理士に相談し、最適な方法を検討されるべきでしょう。
- 生前にできる相続税の対策はありますか?
-
代表的な対策は、以下のとおりです。
- 生前贈与を活用する
- 生命保険に加入する
- 不動産を活用する
生前贈与を活用する
生前のうちに、ご自身の財産をご家族へ贈与し、将来の相続財産そのものを減らしておく方法です。
年間110万円以内なら、贈与税がかかりません。
また、住宅を取得するための資金を贈与した場合、条件を満たせば最大1,000万円まで非課税にできる制度などもあります。生命保険に加入する
生命保険の死亡保険金には「500万円 × 法定相続人の数」という非課税枠があります。現金を保険料として支払っておくことで、非課税枠の分だけ相続財産を圧縮できます。
また、保険金は受取人固有の財産として、遺産分割協議を経ずにスムーズに現金化できるため、納税資金の準備としても極めて有効です。
不動産を活用する
現金や預貯金を不動産に換えることで、財産の評価額を大きく下げることができます。
たとえば、1億円で不動産を購入した場合、評価方法によっては、1億円以下の評価とされるケースがあるため、課税額を圧縮できることがあるのです。
- 生命保険金にも相続税はかかりますか
-
亡くなった方の死亡によって受け取る生命保険金(死亡保険金)は、「みなし相続財産」と呼ばれ、相続税の課税対象となります。
「みなし相続財産」とは、法律上は相続財産ではないものの、亡くなった方の死亡を原因として受け取るため、実質的に相続財産と同じとみなされ、相続税の計算に含められる財産のことです。
ただし、相続税がかからないケースもあります。
- 非課税額(500万円×法定相続人の数)を下回る場合
- 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を下回る場合
生命保険金には、税制上の優遇措置として「非課税枠」が設けられています(※)。
また、相続税自体にも「基礎控除枠」が設けられているため、どちらかの枠内に収まる金額であれば、相続税はかかりません。※生命保険金に関連する、「生存保険金」や「入院給付金」、「特約還付金」といった保険金には非課税枠が適用されません。
- 相続税の申告をしないとどうなりますか?
-
罰則として、「加算税」と「延滞税」を追加で支払うことになります。
①加算税
本来の税額に加え、ペナルティとして「無申告加算税」が上乗せされます。
税率は5%~30%で、申告を行った時期や納付税額に応じて変動します。また、意図的に財産を隠していたなど、悪質なケースではさらに重い「重加算税」(40%)が課されることもあります。
②延滞税
納付期限の翌日から、実際に納付する日までの日数に応じて、延滞税が発生します。
納付期限の翌日から2ヵ月を経過する日までは年7.3%、それ以後は14.6%の割合で課されます。そのほか、「相続税の配偶者控除」や「小規模宅地等の特例」といった、税額を軽減できる特例が原則として利用できなくなるデメリットも発生します。
- 相続税の計算方法を教えてください。
-
相続税の計算は、基本的に以下の流れで行います。
ただし、正確な金額を算出するのは非常に難しいため、できるだけ税理士などの専門家に依頼されることをおすすめします。①正味の遺産額を算出する
②課税遺産総額を算出する
③相続人それぞれの取得金額を算出する
④相続人それぞれにかかる相続税額を算出する
⑤最終的な納税額を算出する①正味の遺産額を算出する
正味の遺産額(課税価格)=プラスの財産-マイナスの財産+7年(3年)以内の暦年課税に係る贈与財産
注意点としては、亡くなる前に贈与された財産も遺産額に含まれる点です。
②課税遺産総額を算出する
課税遺産総額=正味の遺産額(課税価格)-基礎控除額
税法上、相続税の負担を軽減する基礎控除が設けられているため、正味の遺産額から基礎控除額を引くことで課税遺産総額が求められます。
なお基礎控除額は、「3,000万円+(相続人数×600万円)」で計算されます。
③相続人それぞれの取得金額を算出する
各相続人の取得金額=課税遺産総額×法定相続分
算出した課税遺産総額に、法定相続分をかけることで、相続人ごとの取得金額を求めます。
④相続人それぞれにかかる相続税額を算出する
各相続人の相続税額=各相続人の取得金額×税率-控除額
取得金額に所定の税率をかけて、相続人ごとの相続税額を求めます。
税率は、相続税の早見表から確認できます。⑤最終的な納税額を算出する
納税額=相続税の総額×実際に取得した財産の割合-特例・税額控除
最後に、財産の取得割合や控除制度などを考慮して、最終的な納税額が算出されます。
- 相続税の申告はどんな場合に必要ですか?
-
相続などによって取得した財産の総額が、税法上の基礎控除額を超える場合です。
基礎控除額は、以下の計算式で求められます。基礎控除額 = 3,000万円 + (600万円 × 法定相続人の数)
例:法定相続人が配偶者と子2人(計3人)の場合
3,000万円 + (600万円 × 3人) = 4,800万円その後、預貯金や不動産などのプラスの財産から、借金といったマイナスの財産を差し引いて、遺産総額を計算し、先ほどの基礎控除額と比較します。
ただし、税法上の「特例」を利用することで、相続税がかからなくなる場合もあります。
相続税の計算は非常に複雑なため、できるだけ税理士などの専門家へ相談されたほうがよいでしょう。
まずはお気軽にご相談ください。
朝9:00 ~ 夜10:00・土日祝日も受付中
0120-818-121